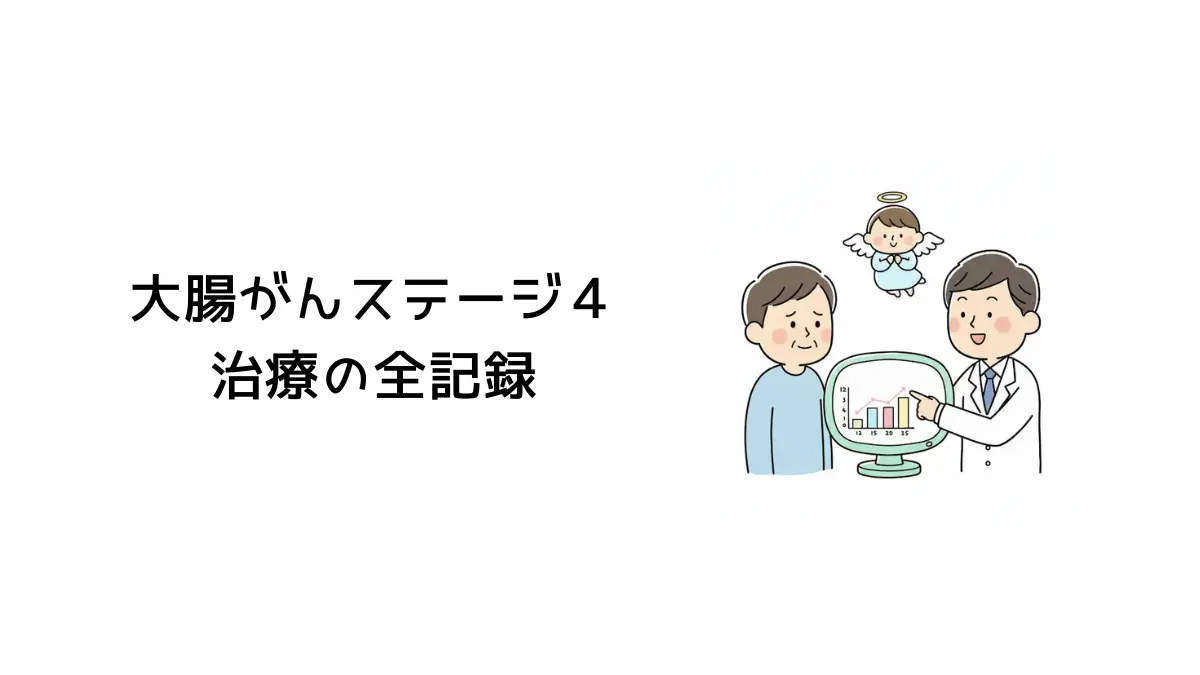現在進行形で大腸がんを治療中のわたし、抗がん剤の副作用について生の声をお届けします。症状がたくさんあるので、一つひとつにキチンと対処するのは大変です。
どんな副作用があるの?自分にも耐えられる?
と、大きな不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
私自身もそうでした。
強い吐き気や苦しみに耐えられるのか?
すごく不安でした。しかし、今の大腸がんの抗がん剤はそれほど吐き気はありません。ともに大腸がんを治療している仲間に聞いても吐き気は聞かないです。それよりも手足の痺れですね。
この記事では、私が大腸がんの治療で経験している主な副作用と、医師や看護師さんから教わった対処法についてまとめました。
これから治療を始める方、今まさに副作用と闘っている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
皮膚のトラブルについて
多くの抗がん剤で起こりやすい副作用の一つが皮膚のトラブルです。特に顔や胸、背中にニキビのような発疹が出たり、全身が乾燥してカサカサになったり、かゆみを伴うこともあります。
薬剤師さんに聞いたところでは、「分子標的薬」が皮膚に悪さをするようです。
ベクティビックスの副作用
「がん」はどうやって治すのか?(国立がん研究センター編)
- 皮膚障害
- 低マグネシウム血症
- 口内炎
わたしは、湿疹やニキビのような症状が、顔、胸、背中、太ももにあります。顔を洗ったりタオルで拭くだけでも血が出たりすることもあるので、強くこすったりしないよう、刺激しないようにしています。
私の対処法
看護師さんに相談したら皮膚科の受診をおすすめされました。皮膚科では保湿剤やステロイドを混ぜた塗り薬を処方してもらっています。
とにかく保湿が大事なんだと口を酸っぱくして言われています。保湿剤を塗りたくってくださいと。

わたしは、処方薬と市販の保湿クリーム「ニュートロジーナ」を随時塗っています。処方薬は伸びが悪くて塗りにくいですが、ニュートロジーナはスーッと伸びてくれます。
朝昼晩となっているせいか、看護師さんにも「副作用が軽くていいですね!」と褒められています。
医師の話では、市販の保湿クリームよりもヒルドイトといった医薬品の方がやはり保湿効果が高いようです。定期的に皮膚科に通って処方薬は切らさないように気をつけています。
紫外線対策について
これは日傘に頼っています。なるべく日本メーカーで軽量なもの、ということでモンベルの晴雨兼用のトラベルサンブロックアンブレラを愛用しています。

159gとスマホ(iPhone Air:165g)より軽く、荷物を軽くしたいわたしの愛用品となっています。
口内炎について
口の中の粘膜が荒れて、赤く腫れたり、口内炎ができたりします。特に舌の周りにできやすい。
私の場合は、口内炎が酷くて痛みがあり、舌も思うように動かなくて会話しにくいこともあります。
冷たいものは痺れて食べられず、醬油や塩味の料理を食べると舌が千切れるかのような痛みがあります。看護師さんに相談して、AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」といううがい薬を処方してもらっています。

あとはひたすら歯磨きです。口の中を清潔にするよう意識しています。口の中が気になったらとにかく歯磨き。この歯磨きグセをつけてから痛みも軽くなったと個人的に感じています。
指先の痺れについて
手足の指先が「ピリピリ」痺れたり、感覚が鈍くなったりします。ボタンがかけにくい、文字が書きにくい、小さな物をつかみにくい、といった日常生活への影響が出ることがあります。

わたしも、冷たいものを触ると指先がしびれます。卵を割るような短い時間でも指先がジンジンします。冬場は手袋をしていないと指先がビリビリしてしまう。
なるべくボタンのない服を選んで、指先を刺激しないよう趣味のギターやピアノはお休み中。しびれ防止の薬はあるようですが、処方してもらっていません。
 筆者
筆者2025年12月現在、しびれの原因「エルプラット」を中止しているので、今後は治まっていくと思っています。
爪の変化について
爪が黒ずんだり、茶色っぽく変色したり、乾燥して割れやすくなったり、筋が入ったりします。爪の周りが炎症を起こして痛む(爪囲炎)こともあります。
爪囲炎はいつの間にか腫れて、いつの間にか血が出て、地味に痛い、そんな炎症です。これが手足問わずに指先にできています。


あれ?なんか痛い、と思って指を見るとひび割れしていたりします。しびれと合わさって不快感が強い。
看護師のアドバイスに従って、寝る前に皮膚科で処方してもらった薬を多めに塗り、手袋をして寝ています。多少良くなっているような感じがします。
ひどいときには痛むので、指先に防水の絆創膏を貼って刺激から守るようにしています。
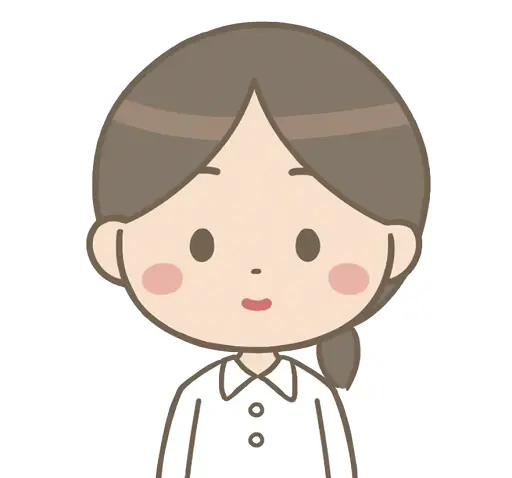
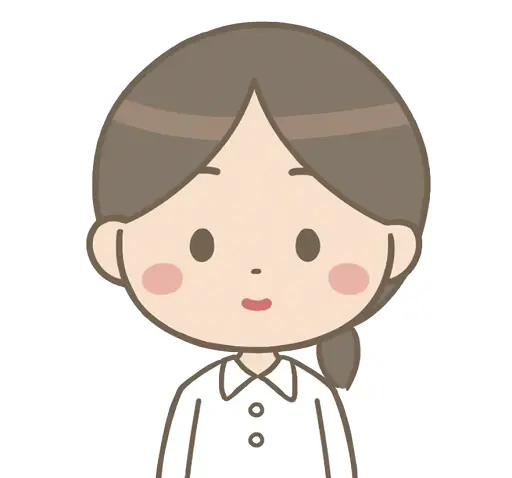
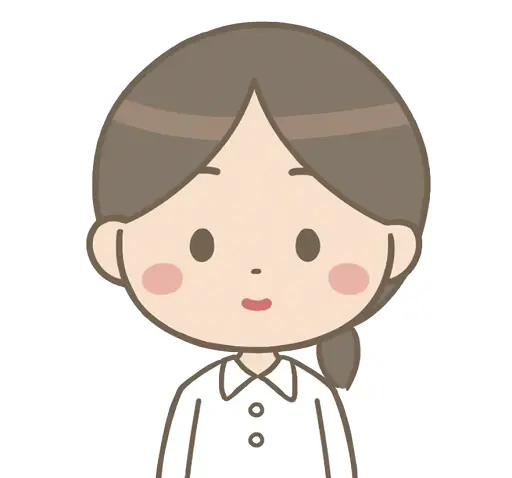
爪から肉を引き離すように絆創膏を貼るといい
看護師さんからアドバイスもいただいています。絆創膏を貼る際には意識してみてください。
便秘について
抗がん剤の種類や、副作用止めとして使われる薬の影響で、腸の動きが悪くなり便秘になることがあります。
これは皮膚の炎症と同じくらい辛い。私の場合は、もうお腹がパンパンになって息苦しくなるほどです。抗がん剤を投与すると3日くらいは一切出なくて辛い。
医師に相談して下剤を倍量に増やしてもらってからは、比較的スムーズに出て楽になりました。もっと早めにお願いすればよかったです。


あとは、なるべく毎日歩いたり自転車に乗ったりして運動するようにしています。2025年末から割とスムーズに便が出るようになって、かなり楽になりました。
脱毛について
大腸がんの治療で使われる抗がん剤は、乳がんなどで使われる薬に比べて、完全な脱毛が起こることは少ないとされています。しかし、薬の種類によっては、髪が細くなったり、全体の量が減ったり(薄毛)、部分的に抜けたりすることがあります。
この脱毛については、看護師さんに相談しても対処法はなさそうです。坊主にするのがおすすめ、というのが唯一のアドバイスだったように思います。
なので6回目の抗がん剤の後に、自分でバリカンで坊主にしました。シャンプーやボディソープは無添加のものを使って刺激しないようには気を付けています。
9回目の抗がん剤の前に実家を訪ねた際、母に



毛が生えてきたわね!
と言われました。確かに抜け毛が減りました。看護師に伝えると、
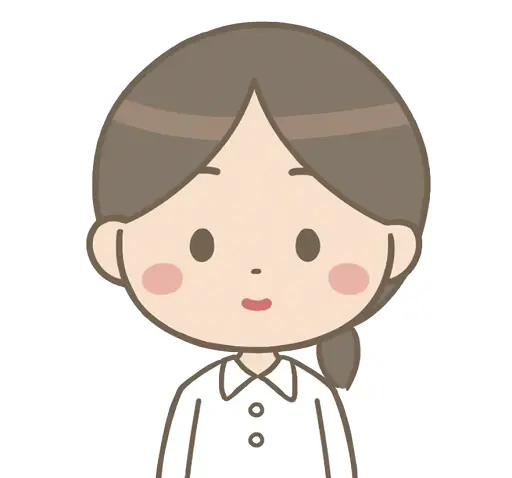
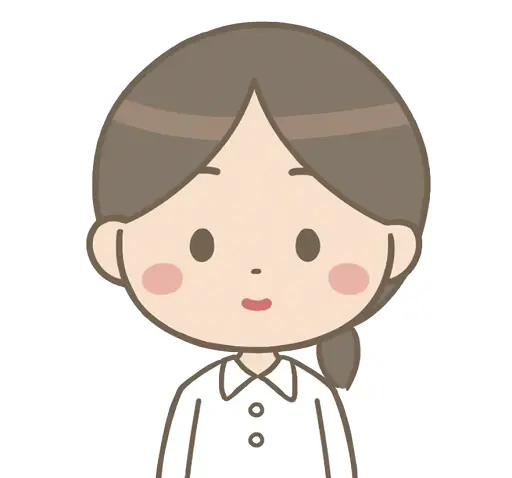
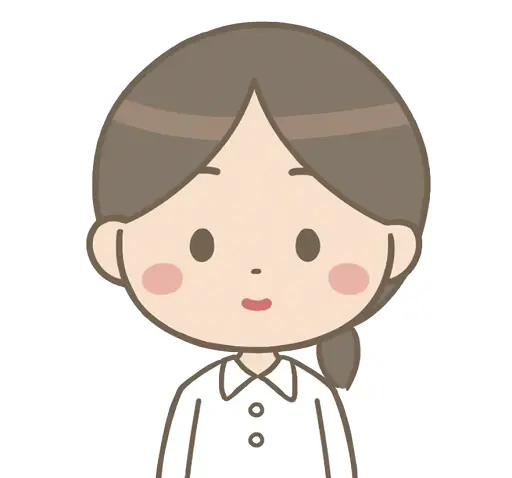
脱毛が止まって毛が生えてきました!っていう方多いですよ。発毛と抗がん剤のサイクルの関係で脱毛が止まったりするみたいです
と教えてもらいました。2026年現在も地味に伸びてきています。ボリュはなくてペチャンコですけどね。
まとめ
抗がん剤の副作用は、いくつかの症状が同時に出てくるので辛いです。心身ともに滅入ってしまうこともありますが、一つひとつの症状にきちんと向き合って適切に対処していくしかありません。
保湿して歯磨きにうがい、紫外線を避けて、食後の薬を忘れずにと、気を付けることが多いです。正直、何回か薬を飲み忘れたりもしてます。でもそんな自分も受け入れつつ、この長旅を続けていくつもりです。
一方で、



抗がん剤をやめたいな、、、
という葛藤に苦しむこともあります。
そういう時は、医師や看護師さんに正直に思いを伝えるようにしています。抗がん剤の効用を統計データで教えてもらってモチベーションを回復させたり、副作用への対処法を教えてもらったりして乗り越えています。
大切なのはひとりで我慢しないことだと思います。気になる症状があれば、どんな些細なことでも医師、看護師、薬剤師に伝えてください。経験豊富な人に相談して教えてもらうのが一番です。あなたに合った最善の方法を一緒に考えてくれます。
抗がん剤の副作用について、私なりの対処法をご紹介させていただきました。あなたにとって副作用が少しでも穏やかになるよう心から願っています。